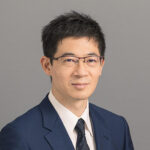展示テーマ
マーク表示について

このマークは、慶應義塾保有の特許案件が含まれていることを示します。技術の利用に関するお問い合わせは、会場内の連携相談窓口で承ります。

相互理解に向けたインタラクション技術


人と人、人とAIシステムの相互理解に向けたインタラクション技術について展示・説明します。聞き逃しなどで生じる誤解の可能性の発生を指摘するシステムSCAINsプレゼンター並びに、店舗内での接客ロボットを想定した、少数サンプルでの顧客の好み推定と商品推薦を行う技術を中心に展示を行います。

人と共生できるAIには,日本ならではの「おもてなし」の能力が必要不可欠であり、この能力は次世代型AIである高度な自律性と汎用性を持つAIそのものです。今回は「おもてなし」のコンセプトデモと、自律汎用AIの中核である、AIが状況を理解しての適切な行動を選択する技術をわかりやすく説明します。


本展示では、データセンタ・AIネットワークのさらなる高速化に必要とされる光インターコネクションのためのポリマー光導波路デバイスの展示、ならびにその作製法であるモスキート法の実演を致します。これらの導波路が可能にする高密度3次元光配線技術をご紹介します。

集積光周波数コムを用いた波長多重伝送・テラヘルツ波伝送


シリコンフォトニクスなどと集積が可能な超多波長光源である集積光周波数コムについて紹介します。集積光周波数コム光源による波長多重光伝送とテラヘルツ波伝送についてそれぞれ説明します。


光ビッグデータの遠隔共有による次世代量子計測・量子通信技術の確立

量子技術を成功に導くには、光量子であるフォトンの正確な操作が鍵となります。本プロジェクトでは、膨大な情報量を持つフォトンの計測データ(光のビッグデータ)を遠隔地間で共有することで、生命医療、情報ネットワーク、基礎理工学の各分野で、新しい量子計測・量子通信技術を確立することを目的とします。

イベントカメラを用いた人物形状・姿勢推定


イベントカメラという,時系列的な輝度の変化のみを捉えるカメラを用いて手指や全身を含む人物の形状や姿勢の推定を行う手法を紹介します。イベントカメラの特徴を活かして、暗所環境や高速な計測が必要なシーン、省電力に計測を行いたいシーンにおいても人物の状態推定を可能にします。

材料開発をはじめとした各種製造業におけるDX推進により、ブラックボックス最適化の需要がますます高まっています。我々は、機械学習技術とイジングマシンとを組み合わせたブラックボックス最適化手法FMQAと呼ばれる方法を提案し、その応用範囲を広げる研究開発を行っています。

量子コンピュータと従来計算機とを組み合わせた「量子・古典ハイブリッド計算システム」の構築を目指した研究開発を行っています。特に、量子・古典ハイブリッド計算システムのポテンシャルを最大限引き出すためのアルゴリズム構築ならびに量子・古典ハイブリッド計算システムに適した応用探索を進めています。


日常空間から宇宙まで: 画像・言語を扱うマルチモーダルAI技術


身近なデバイスから脳活動・宇宙までを解析するマルチモーダルAI技術を紹介します。画像と言語の基盤モデルを用いた実世界検索エンジン、専門家予測を凌駕するAI太陽フレア予測技術、脳波の深層学習と大規模言語モデルによるBMIシステム、画像キャプション評価システムを展示します。


アナログ光ファイバ無線(RoF)システムについて、大電力伝送光ファイバ無線技術、遠隔多チャンネルアンテナ技術、狭小セルに対する高機能RoF制御技術を開発しています。これにより、周波数利用効率の向上、RoFシステムのキャリア間共有の実現、基地局信号処理部の低消費電力化を実現します。



人工嗅覚センサ





⼈⼯知能が⾼度な情報処理をするためには、学習に⽤いるデータが必要になります。⽥中研究室と石黒研究室では、新材料で構成された低消費電力・高集積可能なデバイスを⽤いて⽇常空間内の様々な物理的・化学的なデータのセンシングを⾏っています。

AIを支援するネットワーク型情報探索


適切なデータが提供されてこそAIは機能します。本研究は、AIに提供する信頼性の高い情報を安全かつ高速に探索する技術です。具体的には、潜在的な情報源であるデータベース等を緩やかにグラフとして相互接続する情報ネットワーク構築技術と、高い透明性と安全性を兼ね備えたパーソナライズ可能なグラフ解析技術です。


LiDARを用いた見守り技術

本研究では、LiDAR(Light Detection And Ranging)を用いた見守り技術を紹介します。LiDARを用いることで、カメラと違いRGB画像を用いないためプライバシーを守りつつ、転倒などの検出が可能です。また、歩行の不安定性や人物特定など、様々な応用が可能です。


ミリ波レーダを用いた見守り技術

本研究では、ミリ波レーダを用いた見守り技術を紹介します。カメラのようなRGB画像を用いないため、プライバシーを守りつつ、転倒などの検出が可能です。自宅や病院、介護施設等、様々な場所で使用可能です。


AIを用いた認知症検出技術

本研究では、AIを用いた認知症検出技術を紹介します。顔画像を直接用いるのではなく、FaceMeshを用いて得られる顔のキーポイントに基づき認知症を検出します。そのため、プライバシーを守りつつ、環境光などによる影響を除去できます。また、音声やテキストなどからも認知症を検出することが可能です。

本ブースでは、事実上あらゆる立体を自動で折る技術Inkjet 4D Printを紹介します。これは、インクジェット印刷を施した熱収縮シートを加熱することにより、従来手作業で折ると1時間〜10時間ほど必要だった折紙を10秒程度で折る技術です。会場では、折紙の変形デモと展示を実施します。

ダイナミックロケーターによる自己組織化ネットワークコントロール型自動運転プラットフォーム
近年フィジカル空間からの膨大な情報をサイバー空間に集積し、解析しフィードバックするサイバーフィジカルシステム(CPS)が提唱されています。本研究では動的に変化する道路状況を把握し、ロケーターを元にした特定の位置にいる車両グループを制御するネットワークコントロール型自動運転の可能性を紹介します。

安全で効率的な協調走行のための車両走行制御とV2X通信技術
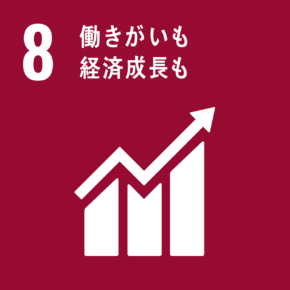


自動運転車が安全でかつ効率的に車間通信や経路探索を行うための制御について研究しています。自動運転による交差点通過や車道のレーン変更で生じる、衝突やブレーキの多発などの問題をシミュレーションを用いて検証し、適した通信プロトコルや経路制御を考えます。






応用抽象化と総合デザイン

「応用抽象化と総合デザイン」は自然現象に対して「無限」に細かくアナリシスを行う理学と、人工物を付加して所望の機能をシンセシスする工学について、両学問の強みを最大限に活かすことを目指す新しい概念です。複雑化された機能をシンプルに実装するための波動制御や要素記述法について紹介します。

環境計測技術の展開による社会貢献志向の研究推進



大気中の微小な粒子は生体に曝露され健康に悪影響を及ぼすと懸念されていますが、粒子の有害性を決める要因は未解明です。当研究室では、独自性の高い様々な手法を用いて粒子状物質の有害性の謎を解く鍵を探しています。また国内外の環境問題の解決に、当研究室の持つ環境計測技術の知見をもって貢献したいと考えています。

機能性に優れたフィルターの開発と環境化学的応用



奥田研究室は、フィルトレーション技術により社会・産業・地球環境への貢献を目指す株式会社ROKIと共に、新機能フィルターの開発を進めています。本研究では水溶性ポリマーの膜強度や耐久性を向上させ、医工連携分野を含めた幅広いアプリケーションへの展開を目指します。

環境大気中の粒子の帯電状態の測定法



環境大気中に浮遊するエアロゾル粒子はイオンと衝突して帯電します。この帯電粒子が半導体に付着すると、静電気でホコリを集め、基板を損傷する可能性があります。その影響を評価するためには、帯電粒子の計測手法の確立が重要です。本展示では、個別粒子分析と平行電極板を用いた2種類の計測法を紹介します。

オンラインSDGsプラットフォームの開発による産官学民連携






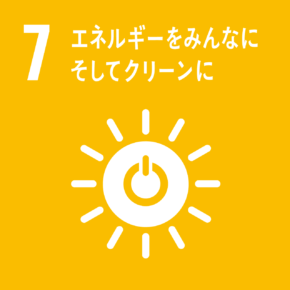
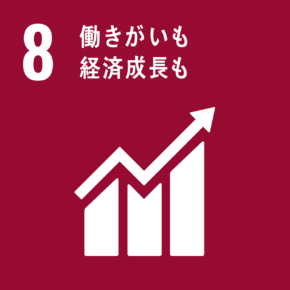









SD(持続可能な開発)に関心のある関係者が集ってその知見や経験を共有することができるオンラインSDGsプラットフォームの開発を行っています。産官学民連携の枠組みの構築を通してオープンイノベーションを促進し、以てSDGsの達成や持続可能な世界の実現に貢献できるような研究開発活動に取り組んでいます。

AIを活用して生産的安全を実践する
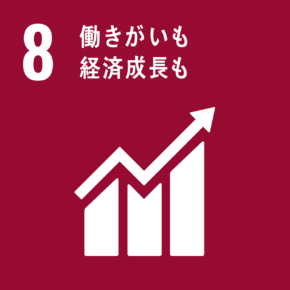

高いレベルでの効率と安全の実現が求められる産業において、生産的活動を犠牲にせず、安全を維持・向上させる”生産的安全”の実践手法を開発しています。ここでは、AIを活用して実践した研究事例について紹介します。

デザインプロセスでUser Experienceを予測する
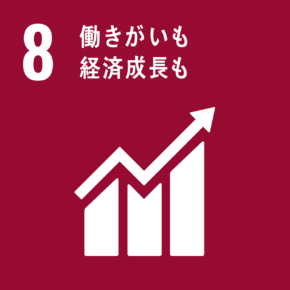

ユーザ・エクスペリエンス(UX)は、手に取ることができない、見ることもできない、本来はユーザしか知りえない”価値”です。この展示では、製品・サービスのUXを、それらのデザインプロセスにおいて予測的かつ定量的に推定する手法について、企業との研究事例を交えて紹介します。

スマートコミュニティのインフラとサービス
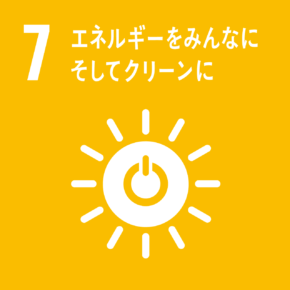


地方自治体や農研機構と共同で進めているスマートタウン・農業を例にスマートコミュニティに関する研究成果および実証について紹介します。この取り組みでは地域情報を取り扱うスマートコミュニティインフラを用いることで情報の匿名化・共有・公開管理などの統括管理を行い、地域密着サービスを安全かつ柔軟に展開します。

人間の認知・行動特性に基づいて、ドライバーの運転支援や自動運転中のドライバーへの情報提供、自動運転車の意図や状態を周囲交通参加者に表明するためのHMI(Human Machine Interaction)の設計や評価に関する研究に取り組み、様々な提案を行っています。


グリーン発電(例えば太陽光)で瞬間にブロックチェーンに発電量、時間、位置が記憶されます。このコントラクトを、ユーザ側が確保できればグリーン電力を利用したと定義されます。距離により、近場のエネルギーを利用し、地消地産を促進し、また、コントラクトは30分で消滅させることで、同時同量制御ができます。
-e1727881520297-150x150.png)
サイバーフィジカルシステムの制御と最適化
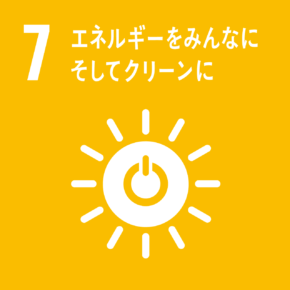


滑川研究室では制御理論のアプローチにより、Cyber Physical and Human System の研究を行っております。特に、分散型電力ネットワークの制御、マルチUAVの分散協調制御、分散推定理論に基づく電力ネットワーク、社会インフラや超スマート社会の最適管理に関する研究を推進しています。

データ解析―顧客満⾜度の数値化、経営・マーケティング・スポーツのデータ解析

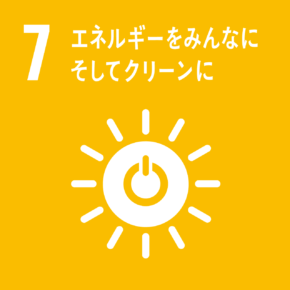
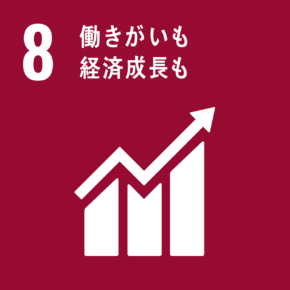





現在、様々な分野でデータ解析の活⽤が注⽬されています。経営やマーケティング分野では、市場環境や顧客調査データ、Web環境を⽤いたデータ分析が⾏われています。スポーツ分野でもデータ解析の活⽤が実践されています。ここでは、顧客満⾜度の数値化、経営、マーケティング、スポーツ等のデータ解析を紹介します。

高感度質量分析インターフェイスの開発


慶應義塾大学先端生命科学研究所にて開発されたシースレスCE-MS法をベースに、メタボローム解析などのオミクス解析の高感度計測が可能となる新規インターフェイスの製造・販売を行っています。

慶應義塾大学におけるイノベーション・エコシステムの拡充
当本部にはオープンイノベーション部門、スタートアップ部門、知的資産部門、戦略企画室があり、これらの組織が協働して大学の研究成果の社会実装を推進しています。各々の部門の役割や取り組みについてご紹介致します。研究成果の社会実装や大学発スタートアップにご興味がある外部の方のご来場をお待ちしてます。
矢上キャンパスオープンイノベーション施設「YIL」・信濃町キャンパスインキュベーション施設「CRIK信濃町」

文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による 産学官連携・共同研究の施設整備事業」において整備を進めている、矢上キャンパスのオープンイノベーション施設「YIL」、信濃町キャンパスのインキュベーション施設「CRIK信濃町」について紹介します。


デジタルミラーアレイと自由形状マイクロレンズアレイを組み合わせることで、3D ボリューム内で光強度を制御できるコンパクトな光学システムが開発されました。これで、光遺伝学による脳治療や光ピンセットによる細胞操作など、医療分野でのさまざまな応用が可能になります。


環境・健康に向けた、より簡単な化学・バイオセンシングデバイスの研究を行なっています。当研究室では、安価で使い捨て可能な紙を基板とし、作製方法に印刷技術を応用することで、フレキシブルなデバイス設計及び大量生産の実現を目指しています。




閉ループ型ノスタルジアBrain Music Interfaceが若年者と高齢者の幸福感と記憶検索能力に及ぼす効果の検証

音楽によるノスタルジアは、高齢者の幸福感と記憶検索能力を向上させます。本研究では、脳波を用いてリアルタイムにノスタルジックな楽曲を選択するBrain Machine Interfaceが、若年層と高齢者の両方でノスタルジア、幸福感、記憶の鮮明さを向上させ、認知症患者への応用可能性を示しました。

社会実装に向けた横断的技術開発 ~医療機器/AI/脳波/触覚~

三木研究室では、MEMS技術を用いてウェアラブルデバイスや人工臓器など、人々の役に立つ革新的な製品の創造に取り組んでいます。

認知機能の変化とともに生じ得るウェルビーイングや生活上の困りごとの変化に対応するソリューション開発のためのデータベース構築

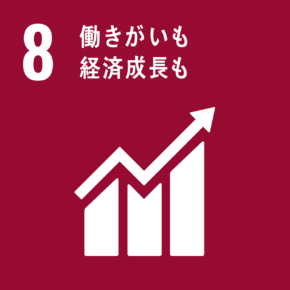

本研究では認知機能の変化とともに生活の質(QOL)やウェルビーイング、生活上の困りごとがどう変化するか、それらの関係に影響を与える因子を探索し、認知機能の低下を経験する方が暮らしやすくなる医療・非医療サービスを生み出すためのデータベースを構築します。

精神疾患の回復や再発予防に向けたソリューション開発のためのウェブ面接中の映像データを含めたデータベース構築

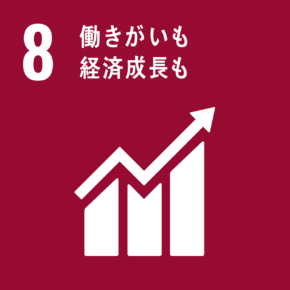



急性期治療後の精神疾患患者を対象に、ウェブ会議システムを用いて定期的に面接を実施し、生活上の課題や困りごとを聞き取り、それに対応する様々な社会サービスの創出を行うためのデータ基盤を構築し、映像・音声データを通じて得られる情報や重症度評価のデータを用いて、回復促進および再発予兆の検出を行います。



身体リンク

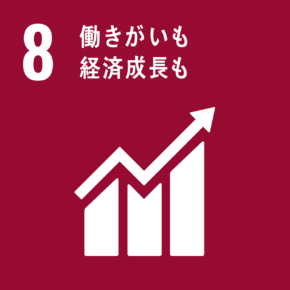

本技術は、機能的電気刺激により身体を直接駆動することを可能にする新たなヒューマンインタフェースです。皮膚表面に貼付した電極に流す電流を制御することで、人と人をつなぐ新たなコミュニケーション形態の創生を目指しています。

機械学習とロボティクスを統合した知能化培養システム


再生医療の発展と普及のためには、人工組織(臓器など)をニーズに合わせて生産し供給することが重要です。本研究では、人間の細胞を培養して人工的な模擬臓器を構築するために、ロボット技術と情報処理技術を融合することで、最適な培養条件を自動的に探索する「知能化」自動培養システムの研究開発を行っています。

光超音波イメージングによるリンパ管の描出

リンパ浮腫の診断や治療にはリンパ管を描出することが大切ですが、リンパ管は無色透明かつ細いため観察が非常に困難です。本研究では、光超音波イメージングという技術を用いて、今までの画像診断装置より詳細にリンパ管を描出し、リンパ浮腫の診断と治療に役立てる臨床応用についてご紹介します。

システムデザイン工学科 小川研究室では、建物利用者の健康で安全な生活を支援する「建築・人連成システム」を提案しています。ロボットやセンサを用いたセンシングにより建築内部環境と人のインタラクションをモデル化し、建築と人、両者にとって最適な空間設計の実現を目指しています。

走査型プローブ顕微鏡による実用ナノ材料の評価
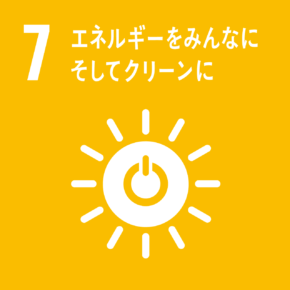

走査型プローブ顕微鏡を用いると、物質をナノスケールで観察することができます。当研究室では触媒、ガス吸着剤、フィラーなど工業利用が期待されるナノ粒子や薄膜などの構造や性質を探求しています。構造を明らかにしたい材料をお持ちの方、プローブ顕微鏡がどういうものか知りたい方、ぜひお立ち寄りください。

KMD Future Crafts プロジェクト: デジタルファブリケーションを活用した衣食住デザイン



慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Future Craftsプロジェクトは、職人的な視点からマテリアルインタラクションについて考え、インターフェイスやファブリケーションなどのテクノロジー開発、メディアアートの表現、キットなどの社会実装の実践を目指します。


MEMS力センサを利用した計測技術


MEMS(微小電気機械システム)の力センサ素子を使った小型で高感度な風速センサや水中流速センサなどを研究開発し、ドローンなどへの応用を進めています。また新しい原理を使った触覚センサやフォースプレートなどを研究開発しています。

人・機械協調のための人肌ヒューマンインタフェースの創出


人と機械の協調には、お互いの物理的な接触(触れ合い)を前提としたシステムの設計が重要となります。本研究プロジェクトでは、機械システムによる人間支援を目的とした、触れ合いなど双方向のコミュニケーションを可能とする機械のための人工皮膚(人肌ヒューマンインタフェース)の構築に取り組んでいます。

理工学部中央試験所について(研究支援拠点(観察・測定・ものづくり))

中央試験所は理工学部の研究活動をサポートする共同利用施設として、様々な分析装置、実験環境を提供しています。機器の操作方法、分析の依頼、研究に関する技術的サポートなど、利用者の多様なニーズに専門スタッフがお応えします。また、中央試験所は産学官連携拠点として学外研究者に機器の利用開放を行っています。
Beyond 5G (6G)時代を支えるフォトニクスポリマー
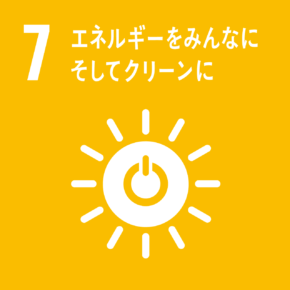
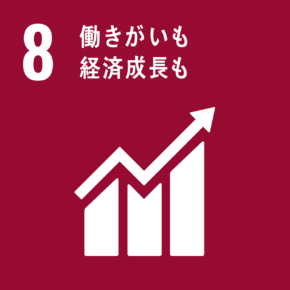


現在、生成AI普及への動きが活発になる一方で、データ通信量の増大により消費電力や通信遅延の増加が懸念されています。KPRIでは、大容量、省電力、低遅延のデータ通信を可能な革新的エラーフリーPOF(プラスチック光ファイバー)やリアルカラーディスプレイを実現する光学フィルム等の研究開発を進めています。


金属ナノクラスターデバイスの技術開発
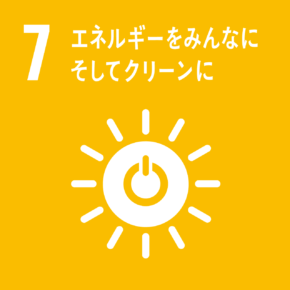


数個から数百個の金属原子が集合した金属ナノクラスターは、構造と電子状態が特異化することによって、新たな触媒活性、光学応答を示します。清浄な金属ナノクラスターを高効率で気相合成する手法と液相合成する手法を構築して、金属ナノクラスターを用いたデバイスや機能材料を開発しています。


TWForkbotによる省スペース搬送システム

人の作業の効率化をはかるためには、人の移動を最小限にできる省スペース空間が望ましいです。そうした省スペース空間において人と共存できる搬送ロボット(TWForkbot)を開発しています。特に、安全かつ安定した搬送動作を行うために力制御の考え方を制御設計に導入しています。



エタノールとポリエチレングリコールというありふれた2つの液体を混ぜて、その薄い膜にレーザ光を照射すると、マランゴニ効果により液滴が生成します。この液滴は勝手に動き出し、カオス的に複雑な運動をすることもあります。多くの液滴を同時に作ると、マイクロロボットや人工生命・人工脳へ応用できると期待しています。


モーションコピーロボットハンド

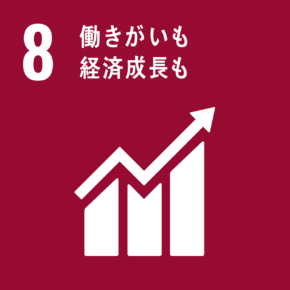

本技術は,人間の手指動作を抽出・保存し、「いつでも・どこでも」再現することを可能にするロボットハンドとその制御の複合技術です。本技術により、接触を含む動作のティーチングの容易化や、実行タスクの複雑化など、ロボットの活躍の場が広がります。


波動制御

本技術は、分布定数系に基づくモデル化方法論により、振動システムの波動制御に成功したものです。時間遅れ要素を基本要素とすることで、制御器の複雑化を回避した安定なシステム構築が可能になります。


不溶性の色素を溶かすタンパク質設計

疎水性の色素化合物を均一に分散させるには有機溶媒を用いる必要があります。これを克服するため、水中でこれらの化合物を溶かす分子の設計を行いました。タンパク質をベースに開発した素材ですので、環境調和性も高い材料です。

量子コンピューティングソフトウェア

量子コンピューティングセンターは、最新のIBM量子コンピューターの実機をクラウドを通して利用できる研究センターです。参画企業と連携しながら、量子コンピューティングソフトウェアの開発・研究を推進します。

新しいナノデバイスや異種の技術を組み合わせていくことで、低消費電力・高性能な情報処理集積システムの実現を目指しています。銅を代替する微細配線、脳神経を模倣したニューロモルフィック回路、ループヒートパイプを用いた三次元水冷技術、クライオCMOSを用いた極低温での量子ビット制御などに取り組んでいます。

パワーエレクトロニクス信頼性解析
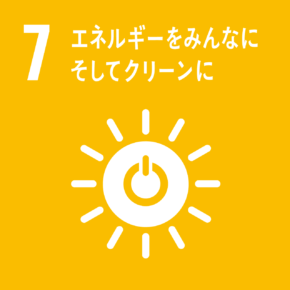
パワーエレクトロニクスにおける重要な信頼性は接合技術にあります。近年銀焼結層による接合が注目されています。強固な接合と高い熱伝導性が期待されておりさらに高温動作にも耐えられることから、SiCチップへの利用も進んでいます。これをマルチフィジックスソルバによって解析します。

エネルギー材料としての層状酸化物と層状複合アニオン化合物(MALC)
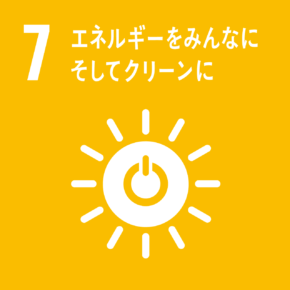

弊研究室内にて研究開発を完結した「混合アニオン化合物鉄系超電導線材とその製造方法 (特許6814007号、特許満了日2036年9月29日)」とともに、同じ研究分野の関連トピックスである「超伝導関連銅酸化物層状化合物と鉄系複合アニオン層状化合物の酸素発生反応電気化学触媒性能」を紹介します。

U字管実験でみるアルカン等の有機溶媒の高分子フィルム透過性

化学工業におけるエネルギー消費の約4割を分離・精製が占めると言われています。このため、省エネを目的として多孔物質を用いた液体分離法が研究されています。類似分子(特に各種アルカン)の膜透過性の違いを、U字管実験で視覚化してみた結果、分離精製に役立ちそうな基本的な課題をいくつか見出しました。

量子化学計算は、触媒や光機能性材料の機能発現機構の理解に大きく貢献してきました。私たちのグループでは、量子化学計算の結果をデータベース化し、機械学習に用いることで、望む性質をもつ材料の発掘や設計を行っています。また、量子化学計算を量子コンピューター上で実施するための方法の開発も進めています。

自然免疫受容体を介して免疫機構の活性化等の調節を行う化合物を開発しており、自己免疫疾患の抑制の可能性やワクチンアジュバント等への展開を行っています。当日はその一端を紹介します。

海洋シアノバクテリア由来抗真菌薬リードの創出


海洋シアノバクテリアが産生する天然物は、抗がん・抗寄生虫活性などの多彩な生物活性を示し、医薬品の候補物質として注目されています。一方で、それらの抗真菌活性については報告が少なく、研究が進んでいませんでした。そこで、本研究では抗真菌活性を有する海洋シアノバクテリア由来の新規天然物の探索を行いました。

次世代生殖医療のための無侵襲卵巣イメージング

近赤外光を用いた光干渉断層計を構築し、卵巣組織に存在する直径20 µm程度の原始卵胞を非侵襲で可視化する技術を研究しています。機械学習を用いて断層画像から卵胞を高精度に検出する手法も併せて提案しています。思春期・若年成人がん患者の卵巣組織を凍結保存する次世代生殖医療への貢献が期待されています。


微細な正弦波構造を有するフレキシブル・ストレッチャブル導電体

パーソナル医療やテーラーメイド医療の普及にはストレスフリーで生体に貼付できるウェラブルデバイスが有用です。我々は微細な正弦波形状を配列した新たな導電シートを開発しました。高い導電性と延伸性を有するため、立体的な曲面を有する生体組織に直接貼付するバイオセンサへの応用が期待されます。