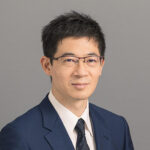展示テーマ
走査型プローブ顕微鏡による実用ナノ材料の評価
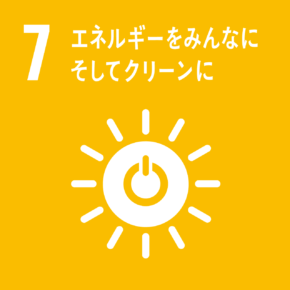

走査型プローブ顕微鏡を用いると、物質をナノスケールで観察することができます。当研究室では触媒、ガス吸着剤、フィラーなど工業利用が期待されるナノ粒子や薄膜などの構造や性質を探求しています。構造を明らかにしたい材料をお持ちの方、プローブ顕微鏡がどういうものか知りたい方、ぜひお立ち寄りください。

KMD Future Crafts プロジェクト: デジタルファブリケーションを活用した衣食住デザイン



慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Future Craftsプロジェクトは、職人的な視点からマテリアルインタラクションについて考え、インターフェイスやファブリケーションなどのテクノロジー開発、メディアアートの表現、キットなどの社会実装の実践を目指します。


MEMS力センサを利用した計測技術


MEMS(微小電気機械システム)の力センサ素子を使った小型で高感度な風速センサや水中流速センサなどを研究開発し、ドローンなどへの応用を進めています。また新しい原理を使った触覚センサやフォースプレートなどを研究開発しています。

人・機械協調のための人肌ヒューマンインタフェースの創出


人と機械の協調には、お互いの物理的な接触(触れ合い)を前提としたシステムの設計が重要となります。本研究プロジェクトでは、機械システムによる人間支援を目的とした、触れ合いなど双方向のコミュニケーションを可能とする機械のための人工皮膚(人肌ヒューマンインタフェース)の構築に取り組んでいます。

理工学部中央試験所について(研究支援拠点(観察・測定・ものづくり))

中央試験所は理工学部の研究活動をサポートする共同利用施設として、様々な分析装置、実験環境を提供しています。機器の操作方法、分析の依頼、研究に関する技術的サポートなど、利用者の多様なニーズに専門スタッフがお応えします。また、中央試験所は産学官連携拠点として学外研究者に機器の利用開放を行っています。
Beyond 5G (6G)時代を支えるフォトニクスポリマー
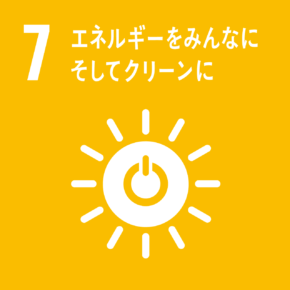
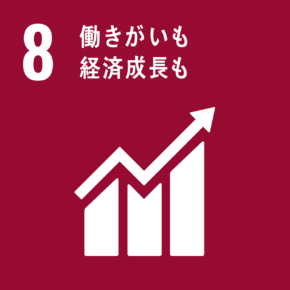


現在、生成AI普及への動きが活発になる一方で、データ通信量の増大により消費電力や通信遅延の増加が懸念されています。KPRIでは、大容量、省電力、低遅延のデータ通信を可能な革新的エラーフリーPOF(プラスチック光ファイバー)やリアルカラーディスプレイを実現する光学フィルム等の研究開発を進めています。


金属ナノクラスターデバイスの技術開発
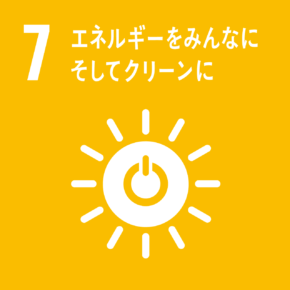


数個から数百個の金属原子が集合した金属ナノクラスターは、構造と電子状態が特異化することによって、新たな触媒活性、光学応答を示します。清浄な金属ナノクラスターを高効率で気相合成する手法と液相合成する手法を構築して、金属ナノクラスターを用いたデバイスや機能材料を開発しています。


TWForkbotによる省スペース搬送システム

人の作業の効率化をはかるためには、人の移動を最小限にできる省スペース空間が望ましいです。そうした省スペース空間において人と共存できる搬送ロボット(TWForkbot)を開発しています。特に、安全かつ安定した搬送動作を行うために力制御の考え方を制御設計に導入しています。



エタノールとポリエチレングリコールというありふれた2つの液体を混ぜて、その薄い膜にレーザ光を照射すると、マランゴニ効果により液滴が生成します。この液滴は勝手に動き出し、カオス的に複雑な運動をすることもあります。多くの液滴を同時に作ると、マイクロロボットや人工生命・人工脳へ応用できると期待しています。


モーションコピーロボットハンド

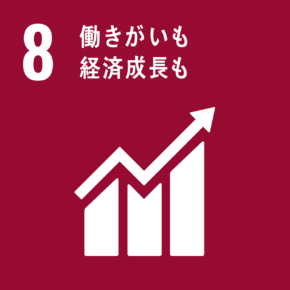

本技術は,人間の手指動作を抽出・保存し、「いつでも・どこでも」再現することを可能にするロボットハンドとその制御の複合技術です。本技術により、接触を含む動作のティーチングの容易化や、実行タスクの複雑化など、ロボットの活躍の場が広がります。


波動制御

本技術は、分布定数系に基づくモデル化方法論により、振動システムの波動制御に成功したものです。時間遅れ要素を基本要素とすることで、制御器の複雑化を回避した安定なシステム構築が可能になります。


不溶性の色素を溶かすタンパク質設計

疎水性の色素化合物を均一に分散させるには有機溶媒を用いる必要があります。これを克服するため、水中でこれらの化合物を溶かす分子の設計を行いました。タンパク質をベースに開発した素材ですので、環境調和性も高い材料です。

エネルギー材料としての層状酸化物と層状複合アニオン化合物(MALC)
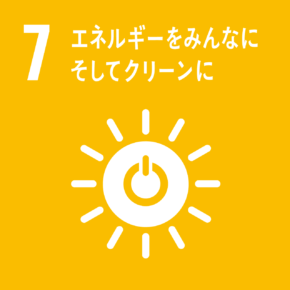

弊研究室内にて研究開発を完結した「混合アニオン化合物鉄系超電導線材とその製造方法 (特許6814007号、特許満了日2036年9月29日)」とともに、同じ研究分野の関連トピックスである「超伝導関連銅酸化物層状化合物と鉄系複合アニオン層状化合物の酸素発生反応電気化学触媒性能」を紹介します。

U字管実験でみるアルカン等の有機溶媒の高分子フィルム透過性

化学工業におけるエネルギー消費の約4割を分離・精製が占めると言われています。このため、省エネを目的として多孔物質を用いた液体分離法が研究されています。類似分子(特に各種アルカン)の膜透過性の違いを、U字管実験で視覚化してみた結果、分離精製に役立ちそうな基本的な課題をいくつか見出しました。

量子化学計算は、触媒や光機能性材料の機能発現機構の理解に大きく貢献してきました。私たちのグループでは、量子化学計算の結果をデータベース化し、機械学習に用いることで、望む性質をもつ材料の発掘や設計を行っています。また、量子化学計算を量子コンピューター上で実施するための方法の開発も進めています。