展示テーマ
環境計測技術の展開による社会貢献志向の研究推進



大気中の微小な粒子は生体に曝露され健康に悪影響を及ぼすと懸念されていますが、粒子の有害性を決める要因は未解明です。当研究室では、独自性の高い様々な手法を用いて粒子状物質の有害性の謎を解く鍵を探しています。また国内外の環境問題の解決に、当研究室の持つ環境計測技術の知見をもって貢献したいと考えています。

機能性に優れたフィルターの開発と環境化学的応用



奥田研究室は、フィルトレーション技術により社会・産業・地球環境への貢献を目指す株式会社ROKIと共に、新機能フィルターの開発を進めています。本研究では水溶性ポリマーの膜強度や耐久性を向上させ、医工連携分野を含めた幅広いアプリケーションへの展開を目指します。

環境大気中の粒子の帯電状態の測定法



環境大気中に浮遊するエアロゾル粒子はイオンと衝突して帯電します。この帯電粒子が半導体に付着すると、静電気でホコリを集め、基板を損傷する可能性があります。その影響を評価するためには、帯電粒子の計測手法の確立が重要です。本展示では、個別粒子分析と平行電極板を用いた2種類の計測法を紹介します。

オンラインSDGsプラットフォームの開発による産官学民連携






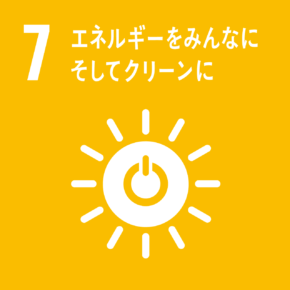
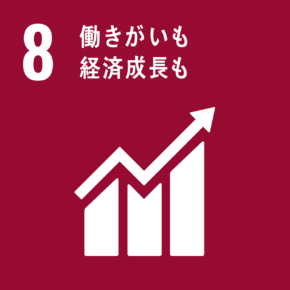









SD(持続可能な開発)に関心のある関係者が集ってその知見や経験を共有することができるオンラインSDGsプラットフォームの開発を行っています。産官学民連携の枠組みの構築を通してオープンイノベーションを促進し、以てSDGsの達成や持続可能な世界の実現に貢献できるような研究開発活動に取り組んでいます。

AIを活用して生産的安全を実践する
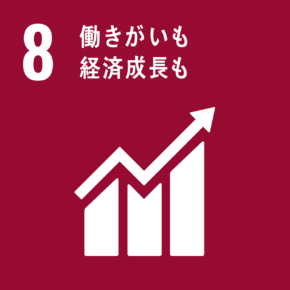

高いレベルでの効率と安全の実現が求められる産業において、生産的活動を犠牲にせず、安全を維持・向上させる”生産的安全”の実践手法を開発しています。ここでは、AIを活用して実践した研究事例について紹介します。

デザインプロセスでUser Experienceを予測する
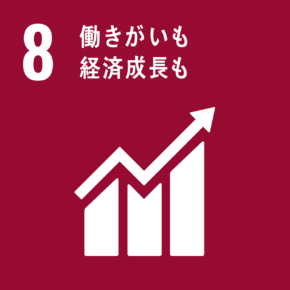

ユーザ・エクスペリエンス(UX)は、手に取ることができない、見ることもできない、本来はユーザしか知りえない”価値”です。この展示では、製品・サービスのUXを、それらのデザインプロセスにおいて予測的かつ定量的に推定する手法について、企業との研究事例を交えて紹介します。

スマートコミュニティのインフラとサービス
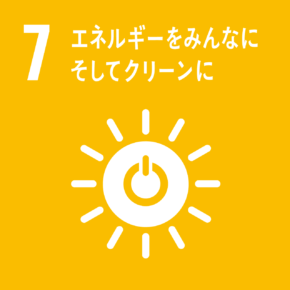


地方自治体や農研機構と共同で進めているスマートタウン・農業を例にスマートコミュニティに関する研究成果および実証について紹介します。この取り組みでは地域情報を取り扱うスマートコミュニティインフラを用いることで情報の匿名化・共有・公開管理などの統括管理を行い、地域密着サービスを安全かつ柔軟に展開します。

人間の認知・行動特性に基づいて、ドライバーの運転支援や自動運転中のドライバーへの情報提供、自動運転車の意図や状態を周囲交通参加者に表明するためのHMI(Human Machine Interaction)の設計や評価に関する研究に取り組み、様々な提案を行っています。


グリーン発電(例えば太陽光)で瞬間にブロックチェーンに発電量、時間、位置が記憶されます。このコントラクトを、ユーザ側が確保できればグリーン電力を利用したと定義されます。距離により、近場のエネルギーを利用し、地消地産を促進し、また、コントラクトは30分で消滅させることで、同時同量制御ができます。
-e1727881520297-150x150.png)
サイバーフィジカルシステムの制御と最適化
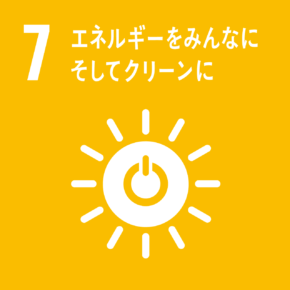


滑川研究室では制御理論のアプローチにより、Cyber Physical and Human System の研究を行っております。特に、分散型電力ネットワークの制御、マルチUAVの分散協調制御、分散推定理論に基づく電力ネットワーク、社会インフラや超スマート社会の最適管理に関する研究を推進しています。

データ解析―顧客満⾜度の数値化、経営・マーケティング・スポーツのデータ解析

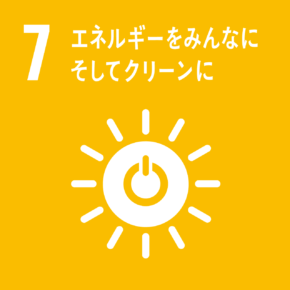
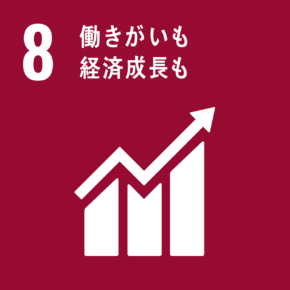





現在、様々な分野でデータ解析の活⽤が注⽬されています。経営やマーケティング分野では、市場環境や顧客調査データ、Web環境を⽤いたデータ分析が⾏われています。スポーツ分野でもデータ解析の活⽤が実践されています。ここでは、顧客満⾜度の数値化、経営、マーケティング、スポーツ等のデータ解析を紹介します。


