展示テーマ

相互理解に向けたインタラクション技術


人と人、人とAIシステムの相互理解に向けたインタラクション技術について展示・説明します。聞き逃しなどで生じる誤解の可能性の発生を指摘するシステムSCAINsプレゼンター並びに、店舗内での接客ロボットを想定した、少数サンプルでの顧客の好み推定と商品推薦を行う技術を中心に展示を行います。

人と共生できるAIには,日本ならではの「おもてなし」の能力が必要不可欠であり、この能力は次世代型AIである高度な自律性と汎用性を持つAIそのものです。今回は「おもてなし」のコンセプトデモと、自律汎用AIの中核である、AIが状況を理解しての適切な行動を選択する技術をわかりやすく説明します。


本展示では、データセンタ・AIネットワークのさらなる高速化に必要とされる光インターコネクションのためのポリマー光導波路デバイスの展示、ならびにその作製法であるモスキート法の実演を致します。これらの導波路が可能にする高密度3次元光配線技術をご紹介します。

集積光周波数コムを用いた波長多重伝送・テラヘルツ波伝送


シリコンフォトニクスなどと集積が可能な超多波長光源である集積光周波数コムについて紹介します。集積光周波数コム光源による波長多重光伝送とテラヘルツ波伝送についてそれぞれ説明します。


光ビッグデータの遠隔共有による次世代量子計測・量子通信技術の確立

量子技術を成功に導くには、光量子であるフォトンの正確な操作が鍵となります。本プロジェクトでは、膨大な情報量を持つフォトンの計測データ(光のビッグデータ)を遠隔地間で共有することで、生命医療、情報ネットワーク、基礎理工学の各分野で、新しい量子計測・量子通信技術を確立することを目的とします。

イベントカメラを用いた人物形状・姿勢推定


イベントカメラという,時系列的な輝度の変化のみを捉えるカメラを用いて手指や全身を含む人物の形状や姿勢の推定を行う手法を紹介します。イベントカメラの特徴を活かして、暗所環境や高速な計測が必要なシーン、省電力に計測を行いたいシーンにおいても人物の状態推定を可能にします。

材料開発をはじめとした各種製造業におけるDX推進により、ブラックボックス最適化の需要がますます高まっています。我々は、機械学習技術とイジングマシンとを組み合わせたブラックボックス最適化手法FMQAと呼ばれる方法を提案し、その応用範囲を広げる研究開発を行っています。

量子コンピュータと従来計算機とを組み合わせた「量子・古典ハイブリッド計算システム」の構築を目指した研究開発を行っています。特に、量子・古典ハイブリッド計算システムのポテンシャルを最大限引き出すためのアルゴリズム構築ならびに量子・古典ハイブリッド計算システムに適した応用探索を進めています。


日常空間から宇宙まで: 画像・言語を扱うマルチモーダルAI技術


身近なデバイスから脳活動・宇宙までを解析するマルチモーダルAI技術を紹介します。画像と言語の基盤モデルを用いた実世界検索エンジン、専門家予測を凌駕するAI太陽フレア予測技術、脳波の深層学習と大規模言語モデルによるBMIシステム、画像キャプション評価システムを展示します。


アナログ光ファイバ無線(RoF)システムについて、大電力伝送光ファイバ無線技術、遠隔多チャンネルアンテナ技術、狭小セルに対する高機能RoF制御技術を開発しています。これにより、周波数利用効率の向上、RoFシステムのキャリア間共有の実現、基地局信号処理部の低消費電力化を実現します。



人工嗅覚センサ





⼈⼯知能が⾼度な情報処理をするためには、学習に⽤いるデータが必要になります。⽥中研究室と石黒研究室では、新材料で構成された低消費電力・高集積可能なデバイスを⽤いて⽇常空間内の様々な物理的・化学的なデータのセンシングを⾏っています。

AIを支援するネットワーク型情報探索


適切なデータが提供されてこそAIは機能します。本研究は、AIに提供する信頼性の高い情報を安全かつ高速に探索する技術です。具体的には、潜在的な情報源であるデータベース等を緩やかにグラフとして相互接続する情報ネットワーク構築技術と、高い透明性と安全性を兼ね備えたパーソナライズ可能なグラフ解析技術です。


LiDARを用いた見守り技術

本研究では、LiDAR(Light Detection And Ranging)を用いた見守り技術を紹介します。LiDARを用いることで、カメラと違いRGB画像を用いないためプライバシーを守りつつ、転倒などの検出が可能です。また、歩行の不安定性や人物特定など、様々な応用が可能です。


ミリ波レーダを用いた見守り技術

本研究では、ミリ波レーダを用いた見守り技術を紹介します。カメラのようなRGB画像を用いないため、プライバシーを守りつつ、転倒などの検出が可能です。自宅や病院、介護施設等、様々な場所で使用可能です。


AIを用いた認知症検出技術

本研究では、AIを用いた認知症検出技術を紹介します。顔画像を直接用いるのではなく、FaceMeshを用いて得られる顔のキーポイントに基づき認知症を検出します。そのため、プライバシーを守りつつ、環境光などによる影響を除去できます。また、音声やテキストなどからも認知症を検出することが可能です。

本ブースでは、事実上あらゆる立体を自動で折る技術Inkjet 4D Printを紹介します。これは、インクジェット印刷を施した熱収縮シートを加熱することにより、従来手作業で折ると1時間〜10時間ほど必要だった折紙を10秒程度で折る技術です。会場では、折紙の変形デモと展示を実施します。

ダイナミックロケーターによる自己組織化ネットワークコントロール型自動運転プラットフォーム
近年フィジカル空間からの膨大な情報をサイバー空間に集積し、解析しフィードバックするサイバーフィジカルシステム(CPS)が提唱されています。本研究では動的に変化する道路状況を把握し、ロケーターを元にした特定の位置にいる車両グループを制御するネットワークコントロール型自動運転の可能性を紹介します。

安全で効率的な協調走行のための車両走行制御とV2X通信技術
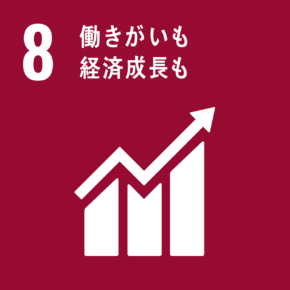


自動運転車が安全でかつ効率的に車間通信や経路探索を行うための制御について研究しています。自動運転による交差点通過や車道のレーン変更で生じる、衝突やブレーキの多発などの問題をシミュレーションを用いて検証し、適した通信プロトコルや経路制御を考えます。






応用抽象化と総合デザイン

「応用抽象化と総合デザイン」は自然現象に対して「無限」に細かくアナリシスを行う理学と、人工物を付加して所望の機能をシンセシスする工学について、両学問の強みを最大限に活かすことを目指す新しい概念です。複雑化された機能をシンプルに実装するための波動制御や要素記述法について紹介します。

量子コンピューティングソフトウェア

量子コンピューティングセンターは、最新のIBM量子コンピューターの実機をクラウドを通して利用できる研究センターです。参画企業と連携しながら、量子コンピューティングソフトウェアの開発・研究を推進します。

新しいナノデバイスや異種の技術を組み合わせていくことで、低消費電力・高性能な情報処理集積システムの実現を目指しています。銅を代替する微細配線、脳神経を模倣したニューロモルフィック回路、ループヒートパイプを用いた三次元水冷技術、クライオCMOSを用いた極低温での量子ビット制御などに取り組んでいます。

パワーエレクトロニクス信頼性解析
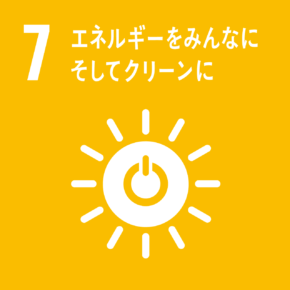
パワーエレクトロニクスにおける重要な信頼性は接合技術にあります。近年銀焼結層による接合が注目されています。強固な接合と高い熱伝導性が期待されておりさらに高温動作にも耐えられることから、SiCチップへの利用も進んでいます。これをマルチフィジックスソルバによって解析します。












-e1727881520297-150x150.png)

