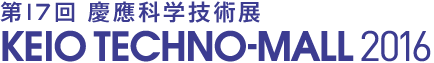基調講演
10:40
▼
11:30
▼
11:30
「大学を中心とした
オープンイノベーションによる産学連携」
オープンイノベーションによる産学連携」
概 要
科学技術の発展のために、大学がその中立性を活かし、海外、インダストリーそして大学の研究、教育のリソースを連携させる中心となることにより、新しいブレークスルーを期待できます。それは多くの船が港に入り荷物のコンテナを交換しながら世界規模で経済が発展していくように、大学が技術や研究の港(ハブ)として科学技術、延いては世界経済の発展に貢献するものと確信しています。
本講演では、慶應義塾大学が進める研究のオープンイノベーションのハブ化戦略についてお話しします。
本講演では、慶應義塾大学が進める研究のオープンイノベーションのハブ化戦略についてお話しします。
11:00-11:30 事例紹介
登 壇 者

ナノイメージングセンター
理工学部 生命情報学科 教授
岡 浩太郎理工学部中央試験所は1960年に設立されて以来、主に学内ユーザーのために分析サービスを行ってきました。これらサービスの他に「産学官連携の場」と「学内装置・施設の有効利用」を目指した取り組みが最近になって着々と進められています。本講演では中央試験所を中心とした昨今の産学官連携の試みについてご説明し、本年7月に開所した「株式会社東陽テクニカ慶應義塾大学理工学部中央試験所産学連携室ナノイメージングセンター」をご紹介します。

ハプティクス研究センター
理工学部 システムデザイン工学科 教授
大西 公平ハプティクス研究センターは、遠方へ力触覚を伝達する新技術(=ハプティクス)を世界で初めて実現し特許化されました。これをシーズとすると、産業分野や医療・福祉分野からの広範なニーズとの整合を図り、いわゆる死の谷を克服しなくてはなりません。このため、センター内に両者の出会いの場である「リアルハプティクス技術協議会」を設置し、企業の積極的な参加を呼びかけています。この協議会では、「リアルハプティクス知的財産権憲章」を制定しており、互恵の精神のもとで参加企業との共同開発が行われます。特に、開発環境の提供、ハードウェアやソフトウェアの開発、応用分野への展開への積極的な支援、国や地方自治体との協力関係構築などを通じて密接な連携を図っています。

超成熟社会創造オープン研究センター
理工学部 情報工学科 教授
山中 直明超成熟社会創造オープン研究センターは、先導研究センター内に開設したオープン研究センターです。少子高齢化と環境やリソースといった制限が発生する超成熟社会は、従来のような大量生産モデルでの発展は望めません。そのため、ICT技術を活用して、サステーナブルな社会を創造するために文理融合、産学連携、国際連携を行うオープンイノベーション研究センターをスタートさせました。本講演ではその枠組みと、代表的なセンター内の研究プロジェクトをご紹介します。