

マーク表示について
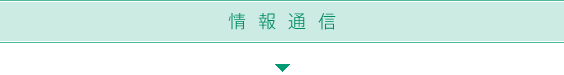
| 実物体入力による仮想映像の生成 |
 |
|||
| 情報工学科 教授 岡田 謙一 | ||||
触れられる実物体を用いたインタラクションでは、ユーザは直感的に作業を行うことが出来る。また拡張現実感は、現実空間に情報を付加しユーザの作業を支援する。本研究では、テーブル上での実物体の動きを仮想空間に反映して提示することで2つの技術の長所を融合し、操作イメージの把握や仮想映像の生成を支援する。
| 環境音の言語的可視化 |
 |
|||
| 情報工学科 准教授 斎藤 博昭 | ||||
私たちは様々な音を聞くことで、周りの状況を把握し、さらにその音を擬音語として表現することで、その時の状況や様子を伝えている。本研究では、環境音をコンピュータに認識させることを目的としており、環境音を擬音語へと変換するとともに、音の特徴を書体表現へと反映させ、環境音を視覚的に認識できるシステムを紹介する。
| Fractional Samplingを用いたMIMO-OFDM受信機 |
 |
|||||
| 電子工学科 准教授 眞田 幸俊 | ||||||
現在無線通信システムで広く使われているのが、OFDM変調です。無線LANやブロードバンド無線システムでは従来複数のアンテナを用いるMIMOシステムが実装されてきました。しかし複数のアンテナを用いると端末の小型化の障害となります。そこでFractional Sampringを用いることによりパスダイバーシチを達成し、通信レートを高速化しながら端末の小型化を図ります。
| アドホックネットワークを利用した 高度道路交通システムやトリアージ支援に関する研究 |
 |
|||
| 情報工学科 准教授 重野 寛 | ||||
アドホックネットワーク技術を、ITS(Intelligent Transport Systems)における車両情報の収集や災害現場におけるトリアージのためのセンサを用いた傷病者情報の収集に応用する。
| GPS受信機を搭載したロボットバイクの自律走行 |
 |
|||
| 物理情報工学科 教授 田中 敏幸 | ||||
近年、次世代の乗用車開発の一環として四輪ロボットカーの研究が進んでいる。しかし、二輪のロボットバイクについては、静止時および低速走行時の安定性の問題からほとんど研究がされていない。この研究では、GPSのナビゲーションによって自律走行するロボットバイクを作製し、新たな応用を開拓することを目的としている。
| テレリアリティシステム |
 |
|||||
| システムデザイン工学科 専任講師 桂 誠一郎 | ||||||
近年、聴覚・視覚に続く第三のマルチメディア情報として、「触覚」を取り扱うハプティクス技術の開発が期待されています。その中で、本研究室では「温もりや柔らかさ」を遠隔地に伝送するテレハプティクスに基づいたテレリアリティシステムの開発を行っています。本ブースでは、新しいテレリアリティを体験して頂きます。
| 電波セキュリティ・見守りシステム |
 |
|||||
| 情報工学科 教授 大槻 知明 | ||||||
カメラを用いずに人の状態を識別可能な電波を用いたセキュリティ・見守りシステムを紹介します。提案システムは、家庭内で事故が多く発生する浴室やトイレの見守りも、カメラを用いずに実現することができます。また、オフィスや車のセキュリティシステムや、省エネのための電源管理システムとしても有効です。
| ロボットによる実世界情報提示 |
 |
|||
| 情報工学科 准教授 今井 倫太 | ||||
携帯ロボットを介した情報提示は、コンピュータ上で閲覧する情報提示と比べ、キャラクタ性・社会性(友人関係等)・身体性(視線の動き、指差し、感情表現、ジェスチャ)を提示内容に付加する事ができる。本研究では、情報提示におけるロボットの新たな可能性を上記3つの観点から提案する。
| 高速列車への高速かつシームレスな インターネット環境の提供 |
 |
|||
| 情報工学科 教授 寺岡 文男 | ||||
300km/h以上で走行する列車に、1Gbps以上の高速でかつシームレスなインターネット環境を提供することが目的です。高速通信のために赤外線通信装置を用い、赤外線通信装置のための高速ハンドオーバ技術を開発しました。第1ステップとして、JR西日本管内の東海道線で行った実験結果を紹介します。
| DiamEAP: オープンソフトウェアによる認証システム |
 |
|||
| 情報工学科 教授 寺岡 文男 | ||||
3GPPやNGNなどに採用され、次世代の認証基盤用プロトコルとして注目を集めているDiameterと、その上で動作する認証プロトコルであるEAP-TLSのオープンソフトウェアを紹介します。これにより、複数の管理ドメイン間におけるユーザのローミングを容易にサポートできます。
| ルータクラウド |
 |
|||
| システムデザイン工学科 准教授 西 宏章 | ||||
ネットワークには、マーケティング上、管理上、セキュリティ上重要な情報が大量に流れています。これまで、情報を届けることに専念してきた情報配信装置(ルータ)を高機能化し、サービスと密接に関連づけることで、インターネットをより使いやすく、魅力ある形へと変えていくルータクラウドの構築技術をご紹介します。
| 潤いのあるコミュニケーションを目指して… コンピュータとの雑談とコンピュータが作るユーモラスなことわざ変形 |
 |
|||
| 情報工学科 教授 萩原 将文 | ||||
コンピュータとの雑談システムでは、コンピュータは電子化されたさまざまな言語データを駆使し、がんばって対話に挑みます。ことわざ変形では、コンピュータはことわざの後半を「すかし」を用いて変え、ユーモラスなことわざ作成をめざします。
| 3Dキャラクタ作成システム |
 |
|||
| 情報工学科 教授 萩原 将文 | ||||
ユーザの感性を反映する3Dキャラクタ作成システムです。ユーザは、システムが提示するキャラクタを評価します。これを何度か繰り返すと、システムは次第にユーザの感性を解析・学習し、好みに合うキャラクタを作れるようになります。
| 分散リアルタイム処理用 Responsive Multithreaded Processor |
 |
|||||
| 情報工学科 准教授 山﨑 信行 | ||||||
RMTPは、1チップに8スレッド同時実行可能な優先度付SMT機構を備えたプロセッサコア(RMT PU)、実時間通信規格(Responsive Link x 4)、各種I/O(Space Wire, PCI-X, IEEE1394, PWM等)、IPC制御機構、及びトレース機能等を集積している。
| 自己組織化省エネルギーネットワーク ~MiDORi~ |
 |
|||||
| 情報工学科 教授 山中 直明 | ||||||
山中研究室が提案するMiDORiは、ネットワーク制御からのアプローチによりネットワーク全体の省電力化を実現する技術です。MiDORiはトラヒックエンジニアリング(TE)を用いてトラヒックを集約し、ネットワークのリンクを積極的に削減することにより省電力化を可能とします。
| 超高速光スイッチによる次世代光ネットワーク技術 |
 |
|||||
| 情報工学科 教授 山中 直明 | ||||||
山中研究室では超高速光スイッチを用いたアクティブ型光アクセスネットワーク(ActiON)を提案しています。本方式は従来のPONと比較して収容加入者数の拡大および伝送距離の伸長を実現します。また、ActiONの拡張として、現在のインターネット網に代わる新世代光クラウドネットワークを紹介します。
| ユビキタスグリッドネットワークによる 次世代クラウドサービス |
 |
|||||
| 情報工学科 教授 山中 直明 | ||||||
山中研究室ではクラウドにおける次世代サービス提供手法として、ユビキタスグリッドネットワーク環境(uGrid)を提案しています。uGridにおいて世界中のデバイスからソフトウェア機能、コンテンツにまでIPアドレスを割り当て、それらをマッシュアップさせるフローパスによって新サービスを提供します。
| EVNO ~Energy Virtual Network Operator~ |
 |
|||||
| 情報工学科 教授 山中 直明 | ||||||
本研究では仮想移動体通信事業者(MVNO)の着想に基づき、既存の電力網を発電システムと送配電システムに分離し、EVNO(Energy Virtual Network Operator)という第三者機関が複数の分散エネルギー源を総合的に管理し仮想的な発電システムを提供する仕組みを提案します。
