

マーク表示について
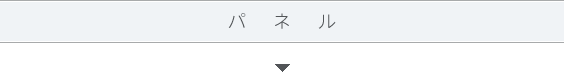
| 抗癌剤リード化合物の創出を指向する シクロブタン誘導体の合成 |
 |
|||
| 応用化学科 准教授 高尾 賢一 | ||||
ペニシリンに代表されるβ-ラクタム系抗生物質と同様に、4員環構造を有するシクロブタン化合物も潜在的に医薬品としての利用価値が高いと考えられる。本研究は、天然物の全合成研究から開発された方法論に基づき、シクロブタン誘導体の合成を多様に行い、その中から抗癌剤リード化合物を探索することを目的としている。
| 生物化学的排水処理へのマイクロバブルの利用 |
 |
|||
| 応用化学科 教授 寺坂 宏一 | ||||
工業的に実用化されている生物化学的廃水処理設備のコンパクト化・高効率化を目指し、新しいマイクロバブル曝気装置を開発した。従来装置に比べ、廃水中への酸素供給性能が大きく改善され、好気性活性汚泥による有機系廃棄物の分解速度が向上した。
| 高温スラリーを利用した新しいCO2分離回収技術 |
 |
|||||
| 応用化学科 教授 寺坂 宏一 | ||||||
地球温暖化原因とされるCO2の大部分は化石燃料燃焼が起源である。その生成時にもつ高い熱エネルギーを維持したまま、純度の高いCO2を分離回収すればその付加価値は非常に高い。本研究ではリチウム複合酸化物粒子スラリーを利用し、高温化で適用可能な新しい懸濁気泡塔型CO2回収システムを提案する。
| エネルギー需要予測とスマートグリッドの分散予測制御 |
 |
|||||
| システムデザイン工学科 准教授 滑川 徹 | ||||||
エネルギー・環境問題への対応や電力の自由化に伴い、スマートグリッドが注目を集めているが、本研究では大規模電力ネットワークの多種多様な発電機をうまく協調させながら、安全性を確保した上で、エネルギー・環境に対して最適な電力エネルギー需要の予測法と発電量の制御法を構築する。
| マルチエージェントシステムと 最適センサスケジューリング |
 |
|||
| システムデザイン工学科 准教授 滑川 徹 | ||||
制御理論・状態推定理論と通信技術を融合したアプローチにより、革新的なセンサネットワーク制御系を構築することを目的とする。複数のセンサエージェントに対して統合的な分散最適センサスケジューリングアルゴリズムの開発と、それを用いたマルチセンサエージェントシステムを構築する。
| 新高温超伝導物質の探索と超電導ケーブルの作成 |
 |
 |
||||
| 物理情報工学科 専任講師 神原 陽一 教授 的場 正憲 |
||||||
超伝導体はある温度(Tc)以下で電気抵抗がゼロになる物理現象です。この性質を利用した送電線は送電ロスの最も少ない究極の省エネ技術といえます。我々は、(A)無機化学に基づく新高温超伝導物質の探索と、(B)パウダーインチューブ法による超伝導線材の開発、の2つを主目的に研究を進めています。
| 熱電変換技術で地球を救う! |
 |
 |
||||||
| 物理情報工学科 教授 的場 正憲 専任講師 神原 陽一 |
||||||||
持続可能な社会の実現のためには、廃熱を高効率で再資源化できる画期的発電効率をもった新しい発電エネルギー変換材料の探索・開発が必要不可欠です。そこで、私たちは、熱電材料未開拓物質群である層状混合アニオン化合物を中心に、高効率熱電エネルギー変換材料の探索・開発を行っています。
| ナノカーボンエレクトロニクスによる未来への期待 |
 |
|||
| 電子工学科 教授 粟野 祐二 | ||||
カーボンナノチューブやグラフェンなど、ナノカーボン材料は、他の物質よりも桁違いに優れた特長を持っています(電気伝導1000倍、熱伝導10倍、他)。ここでは、これらの新材料を将来のエレクトロニクスに活かすための試みとして、カーボンナノチューブやグラフェンの研究についてご紹介します。
| 小口径サブミリ波 ―テラヘルツ帯伝播望遠鏡搭載の分光計システム |
 |
|||
| 物理学科 助教 田中 邦彦 | ||||
宇宙からの光をとらえ、銀河系・宇宙の構造を解明することは、人間のもっとも基本的な科学的好奇心の顕われである、現在最先端にあるのはサブミリ―テラヘルツ波の観測であり、そのための観測装置が世界各地で競って開発されている。本研究では、気球搭載型小口径電波望遠鏡の開発、特に分光装置の開発を行っている。
| マイクロ波磁気デバイス応用に向けた 微小磁性体における磁化ダイナミクスの研究 |
 |
|||
| 物理学科 准教授 能崎 幸雄 | ||||
10億分の1秒以下で高速に記録する次世代ハードディスクでは、磁化の歳差運動があらわになるため、高機能・高性能化に向けて磁化ダイナミクスの理解が不可欠です。展示では、マイクロ波アシスト磁化反転という磁化の歳差運動を積極的に利用した新しい超高密度記録技術を紹介します。
| 商用CFDによる実用的な気液反応装置設計支援 |
 |
|||
| 応用化学科 助教(有期) 藤岡沙都子 | ||||
代表的な気液接触装置である気泡塔内の気液流動状態をシミュレーションします。大型ベンチスケールでの実験データの活用により、商用Computational Fluid Dynamics(CFD)ソフトを実際に適用する際に問題となる設定パラメータの最適化を行い、実用的なシミュレーション手法を提案します。
| 非線形制御法を使った 非接触観察用AFM用マイクロカンチレバープローブ |
 |
|||
| 機械工学科 教授 藪野 浩司 | ||||
原子間力顕微鏡で生体試料を液中でかつ非接触で観察する場合、高粘性環境下における非接触観察が要求させる。本研究は、カンチレバープローブの発振停止の問題を解決し、微小振幅を持つ安定な振動応答を実現する新しい手法(van der Polオシレータの非線形ダイナミクスを利用した方法)を提案するものである。
| ブロードバンドワイヤレス およびモバイルアドホックネットワーク |
 |
|||
| 情報工学科 教授 笹瀬 巌 | ||||
高速大容量だけでなく、ユーザのパーソナル化・カスタマイズに対する様々な品質要求に対して柔軟に対応できる、安全で信頼性の高いブロードバンドワイヤレス通信方式およびモバイルアドホックネットワークにおける最新の研究成果の概要を示す。
| 通信波長帯における高感度蛍光寿命測定装置の開発 |
 |
|||
| 物理情報工学科 准教授 早瀬 潤子 | ||||
蛍光寿命測定装置は、光エレクトロニクスやマテリアルサイエンス、バイオサイエンスやライフサイエンスなど非常に広範囲な分野で用いられています。我々は、高効率波長変換技術と超高速分光技術を利用し、通信波長帯において高感度・高時間分解能で蛍光スペクトルを測定する新しい技術を提案いたします。
| 模型を用いた共同建築設計方法に関する研究 |
 |
|||
| システムデザイン工学科 助教 アルマザン・ホルヘ | ||||
模型を使った設計プロセスの仕組みを明らかにする試みです。2つの典型的なケースを図式化して分析し、そのワークフローを描き出しました。分析結果から、模型の製作・選定プロセスが設計チームメンバー相互の影響を生んでいることが分かり、チームワークや創造性の向上について新たな可能性を示していると考えられます。
| 都市変化と都市激化 ―交通空間において拡張するエコ・アーバニティの可能性― |
 |
|||
| システムデザイン工学科 教授 ダルコ・ラドヴィッチ | ||||
東京とメルボルンにおいて都市調査・分析を行っています。東京とメルボルンの学生が協働して、それぞれの視点で都市を分析し、分析結果を図式にまとめます。また、調査分析結果を基にして、エコ・アーバニティの観点からメルボルンにおける再開発計画のプランニングを行っております。
| 地震に打ち克つシステムデザイン工学 ―住まいの性能設計のためのリスク評価・説明技術 |
 |
|||
| システムデザイン工学科 准教授 小檜山雅之 | ||||
住まい手が納得・満足する構造性能を実現するための性能設計に関して、表層地盤を考慮した地震被害リスクの評価手法、免震建物の擁壁衝突リスクの評価手法、確率を用いた耐震性能のわかりやすい説明手法について研究を紹介する。
| 太陽光発電システム導入計画に対するロバスト最適化モデル |
 |
|||
| 管理工学科 専任講師 武田 朗子 | ||||
電力調達コストや環境負荷を低く抑えるために、地域で導入する太陽光発電のパネルの大きさを決めるにあたって、太陽光発電の新たな買収制度やCO2削減率を考慮した数理モデルを提案する。また、不確実な日射量に対して、ある範囲で最悪状況が生じる場合を想定した最適化手法(ロバスト最適化)を適用する。
| 螺旋型位相構造をもつ光ビームと 多重臨界反射で見られる巨大横シフト |
 |
|||
| 物理学科 教授 佐々田博之 | ||||
通常の光ビームの等位相面は、光軸に垂直で無数に並んでいるが、これが螺旋構造を持つ光が最近注目されている。偏光と同様左右巻きがあるが、偏光とは独立な自由度で応用研究が進んでいる。本研究では右(左)巻きの光がガラス―空気界面で臨界反射を繰り返すと巨大な横シフトを起こすことを示した。