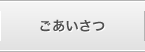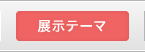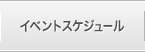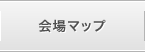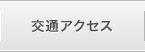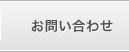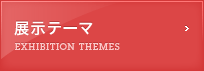マーク表示について
|
医用ハプティクス |
 |
|
| システムデザイン工学科 教授 大西 公平 | ||
|
マスタ・スレーブ型ロボットを用いたバイラテラル制御により、遠隔地への力覚伝達を実現します。本制御は、人間が操作するマスタロボットと遠隔地で作業するスレーブロボットの間で、位置追従と作用反作用の法則を実現します。本研究では、この技術を医療用ロボットへと応用し、力覚伝達による操作者の支援をおこないます。
|
||
|
ナノスケール熱工学によるグリーンLSI |
 |
|
| 電子工学科 教授 内田 建 | ||
|
ナノスケールの電子デバイスを集積化したLSIは、大きな電流をナノスケールの小さな空間に流すため、自己加熱とよばれる発熱現象の影響を強く受けています。我々は、この自己加熱によって生じた熱を、積極的に生かしたり、あるいはうまく逃がしたりすることで、地球環境に優しいグリーンなLSIの実現を目指しています。
|
||
|
チップ間ワイヤレス接続を利用した三次元積層アーキテクチャの研究 |
 |
|
| 情報工学科 教授 天野 英晴 | ||
|
誘導結合を利用した低電力ビルディングブロック型ヘテロジーニアスマルチコアシステムCube-1を提案します。Cube-1は、細粒度パワーゲーティングを適用したMIPS 3000ベースのCPUと低電力指向リコンフィギャラブルアクセラレータを誘導結合を用いたリング状NoCにより結合した構成を持ちます。
|
||
|
拡張ナノ空間プロセシングによる高度光利用の創出 |
   |
|
| 電子工学科 准教授 田邉 孝純 システムデザイン工学科 准教授 柿沼 康弘 電子工学科 助教 寺川 光洋 |
||
|
光を用いて高効率なセンシングを実現するためには、光を小さな空間に閉じ込めることで強く測定対象物と相互作用させる必要があります。そのような光を閉じ込める容器を、超精密加工技術を用いて作製し、実際にバイオセンシング応用に用いることを目標とした基礎研究を慶應義塾大学理工学部にて開始しています。
|
||
|
スピンダイナミクスの物理と情報デバイスへの応用 |
 |
|
| 物理学科 准教授 能崎 幸雄 | ||
|
強磁性体の電子スピンは、磁化の源であり、GHz帯の固有共鳴周波数を持ちます。我々の研究室では、これらの性質を利用して書き換え可能で不揮発、かつ高速動作可能な新しい情報デバイスの開発を進めています。次世代の磁気記録方式や、電子スピンの位相を利用した情報演算の研究について紹介します。
|
||
|
脱レアメタル対極を用いたフレキシブル色素増感太陽電池 |
 |
|
| 物理情報工学科 准教授 白鳥 世明 | ||
|
現在、色素増感太陽電池の対極にはレアメタルが用いられています。更に、作製過程に真空が用いられていることもコストが大きくなる原因となっています。本研究室では導電性高分子とナノ銀ネットワーク電極を複合させることで、常温常圧下で脱レアメタル対極を作製し、フレキシブルで安価な太陽電池の可能性を示しました。
|
||