ナノマテリアルとナノ構造表面
ナノ・マテリアル > 工業 特許出願あり


半導体産業から排出されたシリコン廃材へのレーザ照射によるナノファイバー、ナノ粒子、ナノクラスターの生成および高性能リチウムイオン電池や機能性コーティングなどへ応用しています。また、各種素材の表面へナノ周期構造を形成し、親水性や撥水性および離型性などの制御を行っています。

理工学部機械工学科 教授 閻 紀旺 ❏
ホーム | 展示テーマ



半導体産業から排出されたシリコン廃材へのレーザ照射によるナノファイバー、ナノ粒子、ナノクラスターの生成および高性能リチウムイオン電池や機能性コーティングなどへ応用しています。また、各種素材の表面へナノ周期構造を形成し、親水性や撥水性および離型性などの制御を行っています。

理工学部機械工学科 教授 閻 紀旺 ❏

カーボンブラックを充填したゴム複合材料は、繰り返し延伸によってその応力が不可逆変化します。その時の様子をテラヘルツ光で観察することで、延伸と収縮に伴って材料内部の電子の運動状態がどのように変化するかを考察しました。本成果は、新しいゴム内部状態の診断方法としての活用が期待されます。

理工学部物理学科 教授 渡邉 紳一 ❏


エントロピーが増大すると、ものが混ざるように思われるかもしれませんが、ナノスケールの空洞を用いるとエントロピー増大を利用して液体分離ができると考えられます。我々は、新しい液体分離の考え方を実験によって提唱しています。これは、たとえば生命現象がエントロピー増大と逆向きに感じられることと関係しています。

理工学部物理学科 専任講師 千葉 文野 ❏

アインシュタインの一般相対性理論は、力学的な回転運動(角運動量)が時空の曲がりを発生し、他の角運動量自由度に影響を与えることを予言しています。このブースでは、物質中の局所的な力学的回転を使って磁気的な回転、つまり磁気を生み出す全く新しい技術を紹介します。

理工学部物理学科 教授 能崎 幸雄 ❏



ソフトマターは機能性材料とも呼ばれ、ゴムや洗剤、化粧品、医薬品など身の周りの多くの製品に用いられているが、分子の構造と物性の間をつなぐ処方箋の大部分は未だ明らかになっていない。私達は分子シミュレーションを用い、材料内部の挙動を再現することで、物性や機能性が発現するメカニズムの解明に挑戦している。

理工学部機械工学科 准教授 荒井 規允 ❏
理工学部機械工学科 助教 小林 祐生


マイクロ・ナノテクノロジーが進展し、細胞膜の構成要素である膜タンパクの機能を活用したin situ核酸シーケンシング等の新奇デバイスが期待されている。そこで本研究では、ガラス基板上に加工したマイクロ・ナノ流路に脂質二重膜と膜タンパク分子を組込む方法を開発した。

理工学部システムデザイン工学科 准教授 嘉副 裕 ❏


水と油になじみやすい部位をあわせ持つ両親媒性分子が形成する、二分子膜が袋状に閉じたベシクルは、水溶性、脂溶性のいずれの物質も封入することができます。このようなカプセルとしての性質をもったベシクルに、pHや温度といった刺激応答性を付与したベシクル型人工細胞の開発事例をご紹介します。

理工学部応用化学科 専任講師 伴野 太祐


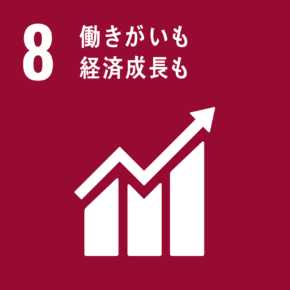



IoTの発展により、4K・8K映像や5Gの普及が著しく進んでいます。本プロジェクトは、大容量、省電力、低遅延のデータ通信を可能とする革新的エラーフリーPOF(プラスチック光ファイバー)やリアルカラーディスプレイを実現する光学フィルム等の実用化に向けて、研究開発を進めています。

慶應義塾大学 教授 小池 康博 ❏


光と電場を使ってコロイド粒子や液滴を駆動し、マイクロロボットとして機能させます。相変化材料フェロモンを組み込んだ蟻ロボットや自由な場所に出現し、形状を変化させるターミネーターロボットなどをご覧いただきます。

理工学部電気情報工学科 教授 斎木 敏治 ❏

グラフェンやカーボンナノチューブなどのナノカーボン材料を用いたチップ上の光電子デバイスを紹介します。デバイス開発・計測はもちろんのこと、得られた物性の理論的な解明、さらにはそれらの実用化研究も進めており、ナノサイエンスの基礎から応用を幅広く手掛けています。

理工学部物理情報工学科 教授 牧 英之 ❏



マイクロ加工技術やマイクロ流体デバイス技術を利用し、機能性ナノ材料(ハイドロゲル、生分解性ポリマー、コロイド粒子、CNTやDNAなど)をデバイス上に統合することで、自然分解型環境センサ、過食センサ、再生医療のための3次元組織構築、生体情報取得ウェアラブルセンサ、などの研究開発を行っています。

理工学部機械工学科 教授 尾上 弘晃 ❏


走査型プローブ顕微鏡を用いると、物質表面を単原子・単分子のスケールで観察することができます。当研究室では触媒やガス吸着剤、単分子エレクトロニクス素子など機能をもつナノ材料の構造や性質を探求しています。ナノスケール構造を見たい材料をお持ちの方、ぜひお声がけください。

理工学部物理情報工学科 准教授 清水 智子 ❏




貝殻は生物が作り出す精密なナノ構造材料です。本研究では、廃棄されている養殖ホタテガイの貝殻を原料として、貝殻のもつ本質的なナノ構造を利用することで多彩な高機能ナノ材料を開発しています。これは、産業廃棄物の有効活用にとどまらず、二酸化炭素の固定化にも寄与する重要な技術となる可能性があります。

理工学部応用化学科 教授 今井 宏明
分子動力学シミュレーションなどの手法を用いて、生体膜や蛋白質、コロイド、高分子などソフトマターと呼ばれる「やわらかいもの」の構造やダイナミクスを研究しています。

理工学部システムデザイン工学科 専任講師 山本 詠士 ❏