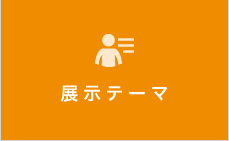マーク表示について
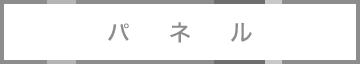
|
シリカ微小光共振器のセンシング応用 |
 |
|
| 電子工学科 准教授 田邉 孝純 | ||
|
従来の光を用いたセンシングでは光と物質の相互作用が弱いために、デバイスのサイズと感度にトレードオフの関係があるという欠点を持っていました。そこで我々は微小空間に光を閉じ込める微小光共振器を用いることで、光と物質の相互作用を高め、小型かつ高感度なセンサを実現しました。
|
||
|
|
 |
|
| 物理学科 准教授 渡邉 紳一 | ||
|
新規光通信波長帯を開拓する光機能回路の開発及び高度化 |
  |
|
| 電子工学科 教授 津田 裕之 電子工学科 専任講師 久保 亮吾 |
||
|
現在、光ネットワークに利用される波長帯は、1530~1625nm帯、及び、1260~1360nm帯に限られています。一方、未開拓の1000~1260nm帯(Tバンド)を利用できれば、伝送容量の更なる拡大が可能なため、Tバンドで動作する良好な特性と信頼性を有する光機能回路の開発を進めています。
|
||
|
計算機シミュレーションを用いた蛋白質分子の動き |
 |
|
| 物理学科 専任講師 光武 亜代理 | ||
|
生体分子の分子シミュレーションは安定性や動きを研究するのに使われています。私は、小さい蛋白質やペプチドの計算機シミュレーションを行ってきました。特に、物理化学に基づいた分子シミュレーションの方法論の開発を行っています。これまでの研究を応用にも繋げていきたいと考えています。
|
||
|
近接場光を用いた高感度単一分子バイオセンサーの開発 |
 |
|
| 電子工学科 教授 斎木 敏治 | ||
|
近年、個別化医療の実現に向けて、高感度なバイオセンサーの開発が注目されています。本研究室では、近接場光を用いた単一分子計測技術を応用して、DNAやバイオマーカーの検出技術の開発に取り組んでいます。本開発技術の特徴は、微細加工技術を使用せずに検出可能であるため、デバイス化に適した技術であることです。
|
||
|
次世代太陽エネルギー変換および エレクトロニクス応用を目指した機能性超分子材料の創製 |
  |
|
| 化学科 准教授 羽曾部 卓 化学科 助教 酒井 隼人 |
||
|
気体燃焼を利用した機能性酸化物微粒子の合成 |
 |
|
| 機械工学科 准教授 横森 剛 | ||
|
|
 |
|
| 応用化学科 教授 朝倉 浩一 | ||
|
自己組織化を利用したマイクロナノシステムとデバイス応用 |
 |
|
| 機械工学科 専任講師 尾上 弘晃 | ||
|
|
 |
|
| 情報工学科 教授 山中 直明 | ||
|
多様な構造型ストレージ技術を統合可能な再構成可能ハードウェア |
 |
|
| 情報工学科 専任講師 松谷 宏紀 | ||
|
FPGAを用いてNOSQL(キーバリュー型、カラム指向型、グラフ型などの構造型ストレージ)のためのハードウェアアクセラレータを開発しています。
|
||
|
輝度指標投影に基づく光センサの三次元位置計測 |
 |
|
| 情報工学科 准教授 杉本 麻樹 | ||
|
プロジェクションマッピングなどの情報環境の映像コンテンツと実環境の物体の位置合わせを実現する手法として、輝度勾配の投影による光センサの三次元位置検出手法について紹介を行います。
|
||
|
|
 |
|
| 電子工学科 専任講師 湯川 正裕 | ||
|
信号処理工学を中心とした数理工学を研究し、情報通信工学・音響工学・脳科学など様々な分野で普遍的に役立つ基盤技術の構築を目指しています。一例として、凸解析と不動点近似を軸に、数理モデルの適応選択問題を凸関数列の漸近的最小化問題として定式化し、その解を適応的に求めるアルゴリズムの構築に成功しました。
|
||